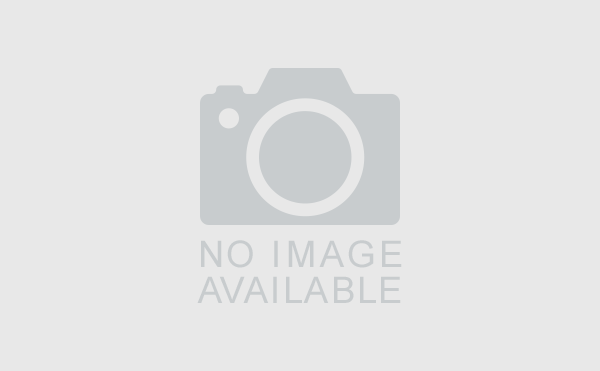2月勉強会(・虐待・不適切ケア・介護困難事例解決ロールプレイ)
◇
各、事業所間の話し合い
◇
エーデルワイスの今後の方向性について共有
◇
Sリーダーより地域交流のご案内
◇
K看護リーダーより感染防止について
防止策の聞き取りと再度の指導強化
◇
満足いく料理の支援について
食材を活かした使い方
今の時期の玉ねぎ・大根・じゃがいもの使い方
◇
虐待と不適切ケア
・
養介護施設従事者等の定義に始まり、
平成18年から有料老人ホームの対象の拡大。
人数が数名でも食事、掃除等の家事または健康管理等のいづれか提供があれば
有料老人ホームに該当し、
高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」に該当し、届け出が為されなくても
老人福祉法に基づく都道府県の立ち入り検査や改善命令の対象となると、
平成21年5月28日付老振発第0528001号「未届けの有料老人ホームの届出促進及び指導等の徹底について」明記。
◇
介護現場においては、
認知症の人を「家族が帰宅するまで鍵をかってほしい」と家族から言われても、
それは、本人の同意も得られず、
訪問介護やデイサービスの場においては、
「はい、わかりました」と言ってしまいがちですが、
高齢者が出られないように
するのには間違いなく、身体拘束に該当するものであります。
◇
しかし、例えば
目の前が道路に面して危険を察する能力が低下した人や徘徊があるならば、
本当にそれで良いのか。
マイナスになる北国においては凍死の危険性もあり、
虐待か、否かではグレーゾーンのようでもあります。
しかしながら、東京での学びの中で弁護士さんの意見では
「やったか・やらないか」というところが問われるとのこと。
このような情報を入れる事も介護現場では大事なことですが、
話し合う場から意見をすり合わせる働きも必要と考えます。
★★★?★★★
いづれにしても、
そのような話し合いが、ケアマネ含む現場にいる人々と話し合うことが一番ですね。
ケアマネの立場からもこのような詳細があるととておわかりやすく、
現場にいる自分等も、自ら学ぼうとしないと情報は一人では入ってきませんね
昨日は、介護現場における具体例テキストから多くの学びをいただきました。
◇
事業所困難事例検討と解決報告
「介護困難です。どうしたらいいのでしょうか」という
切羽詰まった事例から
ロールプレイでご本人になっていただきました。
☆
「本人の立場で考える事と、本人になりきることでは全く違う」とFスタッフです。
「ご飯食べていないけど。どうしてこんなひどいことをするの」と、
朝食後に朝寝をしたご利用者からの言葉です。
ご利用者から受けた言葉が、
本人になりきったスタッフから、
すごいスピードで言葉が飛び出します。
・
・
びっしり詰まった重たいものが吐き出されるようにさえも感じました。
ロールプレイは、
相手を知ることばかりではなく、
心の重たいものも緩和するようであります。
・
☆
課題の解決方法は朝の時間から始まり、
統一したチームケアから「忘れた・時間がずれた」というスタッフから
後手の介護に突入し、多くの時間を割く羽目となったようであります。
思いやりのある先手の介護が必要なことが浸透です。
☆
解決に導く勉強会は、参加者に強く興味をもっていただき集中する事が出来ました。
最後の恒例じゃんけんポン大会は、
幸運の女神が男性と女性2名に舞い降りました。
出張中の方もおりましたが、昨日は22名の方が自主勉強会に参加していただけました。
ありがとうございました。