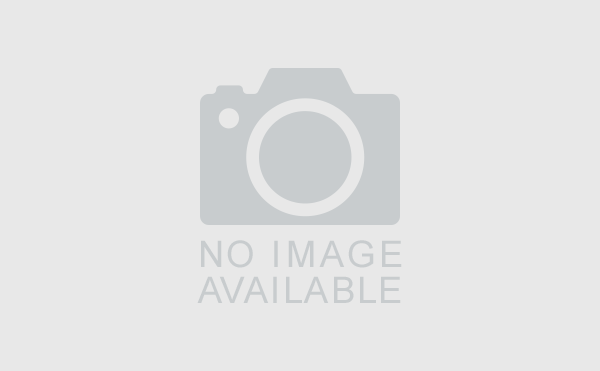子どもも、大人も、話を聞くこと
認知症サポーター養成においての
認知症の人の対応にも
金融機関の窓口の対応にも
子育て中の変化する子どもの対応にも

目線を合わせ話をしっかりくこと、
聞かせていただくことの大事さが述べられている。

上手くことばで伝えられなくても
「だいじょうぶですよ」と言葉にならないやさしさの「気」を送ると
「あーこの人は良い人だ。話を聞いてもらえるんだ」と
体の硬さがやわらぎ、
伝えたいことが言葉になってでてくる。

子どもも
大人も
認知症を患う人も
相手が発するエネルギーは
発することばは優しそうでも
強い拒否のエネルギーを発していると、相手は近づくことはできず
その後に混乱を招くこととなる。
🍓
気分の高揚が激しい認知症の人にでも
立ち去るときには
手を肩の所まで上げ
頭を下げ、心で「それじゃ」と無言で伝えると、
相手も「うん」と頷いていただける。

(1番地 きなこもち)
小学生でも
中学生でも
高校生でも
親に口論で向かってくるときが必要で
心の葛藤を表現している場面であり
無理やり蓋をしてしまうと
高齢になってからも引きずる場面となり
相手を構わず憎しみとなる対象となってしまう場面がある。

(2番地 餅入りおしるこ)
コミュニケーションは、どれだけ多く時間をかけたかではなく、
立ち去る1分でも「お邪魔しました。失礼します」と
その人の存在を認め、
子どもであっても
混乱する認知症の人であっても
自分も含め介護する側、
心配する家族が一方的に優位に立つのではなく
本人の思いをしっかり受け止め
尊敬の心をいかほど注いだかによるものだとやはり現場から教えていただけた。